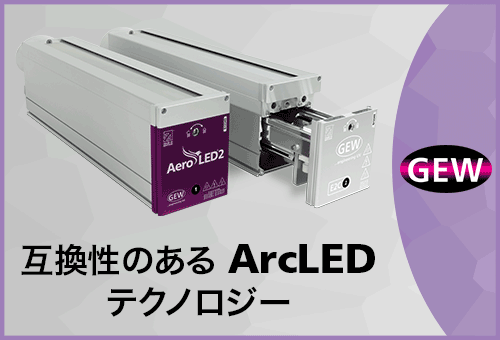▼ダーウィンは190年前の1835年、南米西岸のガラパゴス諸島に上陸。生態系の調査に基づき自然選択説「進化論」を発表した。生き物が変異を経て自然に適応した種のみが生き残るといった理論であり、現代でも生き物の多様性や適応に関するメカニズムのセオリーに位置づけられる
▼不本意ながらも理論の源となった群島名は現在、世界標準から乖離した製品や技術の意を示す。例えば日本の携帯電話「ガラケー」。折りたたみ式で一世を風靡し、さらに多機能化が進められるも、汎用OSや操作性のよいタッチパネル、アプリのダウンロードによるパーソナライズ化などが特徴のスマホにその座を奪われた。国際化が進む通信市場にあって、既存の機能向上だけでは適応できなかった
▼米トランプ大統領は8月1日から、日本の輸入品すべてに25%の追加関税を発表。グローバルサプライチェーンが発達した現代の経済情勢に逆らう政策を強行する。自動車や電子部品、事務用機器など対米輸出比率が高い業種への影響は必至。あるシンクタンクは「2025年のGDPは事実上ゼロ成長の可能性」と分析する。ラベルを製造する企業は、工業分野に限らずゼロ成長の蓋然性を見据えたビジネス戦略の見直しを
▼「最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き残るのでもない。唯一生き残るのは変化できる者」。多機能化・過剰な高品質化は市場ニーズにマッチしているか、低コストのニーズはいずれ淘汰されないかなど、進化論になぞらえていま一度鑑みるべき。重要なのは、技術や機器の最新情報を収集し、また消費者がラベルに求めることを正確に把握したうえで、それらに対応できる企業体制への変革に取り組むこと。ラベルビジネスに携わる企業、そしてラベル業界全体が今後の経済状況に適応するために変化することを期待したい。
(2025年7月15日号掲載)